
どーもパパちんです。
秋の自然遊びのひとつに「クルミ拾い」があります。公園や川原でゴロゴロ落ちているクルミを見つけると、子どもはまるで宝探しみたいに大喜び。
でも、クルミは拾ったそのままでは食べられません。果皮をむいたり乾燥させたり、ちょっとした手間が必要です。
今回は「拾ってから食べられるようになるまで」を子どもと一緒に楽しむポイントとあわせて紹介します。
クルミ拾いの楽しさ

どんぐりや松ぼっくり探しと同じように、落ちているクルミを探すのはワクワク体験。
「どっちがたくさん見つけられるか競争!」なんてルールを作ると、子どもは夢中になります。
でも、クルミ拾いの一番の楽しさは、拾った後に食べれるってことじゃないですかね?
おいしく食べられるって思うと余計に楽しく拾えること間違いなしです!
果皮の処理(親子で分担しよう)
拾ったクルミは外側に果皮がついています。これをそのままにしておくとクルミを乾かすことができません。
果皮を剥いて殻の部分を取り出しましょう。
まだ緑色の果皮がついている状態ではなかなか剥くことはできません。緑色の実を拾ってきた場合はしばらく置いて、果皮が黒くなって柔らかくなるのを待ちましょう。
簡単なのは、すでに黒くなって半分果皮が剥けている状態の実を拾ってくることです。
そうすれば、持ち帰って洗うだけなので、比較的簡単に処理ができます。

- 大人の仕事:果皮をむく(アクで手が真っ黒になるので手袋必須!)
- 子どもの仕事:果皮を取ったあとのクルミを水でゴシゴシ洗う
「きれいになった!」と子どもが達成感を味わえる瞬間です。

洗浄と乾燥

果皮を取ったらよく水洗いをして、しっかり天日干しします。
このとき子どもに「毎日ひっくり返す係」をお願いすると、観察日記みたいで楽しめます。
「昨日より軽くなった?」「乾いてカラカラしてきた!」と変化を感じられるのも学びにつながります。
殻割りに挑戦!
乾燥が終わったら、いよいよ殻を割ります。クルミの殻はとても硬いので、ハンマーや専用のクルミ割り器を使います。
安全に配慮しながら、子どもにも「トンカチでコンコン」と挑戦させると大興奮!
どうすれば上手く割れるかを考えるのも、いい経験になります。
ハンマーで叩く際には指を挟まないように気をつけて叩くようにしましょう。
割れたら、中身を出して、殻と実を分ければ完成です!
殻の中は複雑な形になっているので、中身が残らないようきれいに取り出すようにしましょう。

うちでは殻から実を取り出すのは子どもにやってもらいますが、けっこう細かくて難しいので、子ども達は夢中で実を取り出していますよ!(笑)
おすすめの食べ方
取り出したクルミはそのままローストしてもおいしいし、クッキーやケーキに入れても相性抜群。
そしてパパちんイチオシは… 五平餅のクルミだれ!
すり鉢でゴリゴリするのは子どもにお任せすると、料理にも参加できて楽しさ倍増です。
クルミは殻が硬かったり、ちょっと独特の風味があったりして、子どもだと「食べにくい」と感じることもあります。
でも、自分で拾って、洗って、割って、料理に入れるまで関わると、不思議と「食べてみよう!」って気持ちになるんです。
最初は苦手そうにしていたうちの子も、「自分でゴリゴリしたクルミだれの五平餅」をパクっと食べてくれました。
まとめ
クルミ拾いは「拾う → 洗う → 乾かす → 割る → 食べる」と、子どもが最初から最後まで関われるのが魅力です。
自然の恵みを体験できるだけでなく、「自分でやったから食べてみよう!」という気持ちを育てるきっかけにもなります。
親子で楽しめる秋の自然遊びとして、ぜひ挑戦してみてください。
ではまた。――パパちん
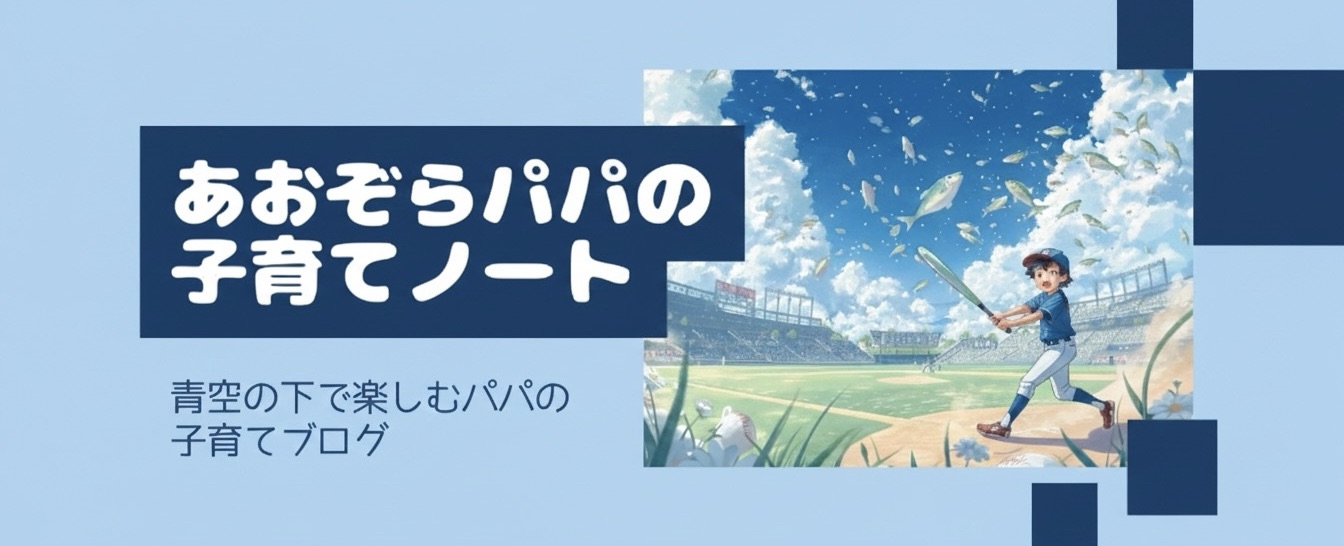





コメント