
どーも、パパちんです。
秋になると子どもと一緒に夢中で拾いたくなるのが「木の実」。どんぐりや松ぼっくりを持ち帰って、家で飾ったり工作に使ったりすると楽しいですよね。
でもそのまま置いておくと……虫が出てきたり、カビが生えたりしてガッカリすることも。
僕も最初は知らずに棚に置いておいたら、どんぐりから小さい虫がポロポロ……(泣)

今回はそんな失敗を防ぐために、「木の実を拾ったあとどう処理して保存すればいいのか」をまとめてみました。
木の実によって処理方法が違う

一口に木の実といっても、それぞれ特徴があります。
- どんぐり … 虫が入りやすい。煮沸すると逆に腐りやすいので注意。
- くるみ … 周りの果皮を取る必要あり。食用がメイン。
- 松ぼっくり … 濡れると「かさ」が閉じる。漂白でアレンジ可能。
- モミジバフウなど小さい実 … 見た目が可愛いけど虫が出やすい。
この特徴に合わせて処理方法を選ぶのがポイントです。
基本の処理方法

水選別(どんぐりにおすすめ)
どんぐりは煮沸すると腐ってしまう可能性があるので、水に沈むものだけを選ぶのがおすすめ。
ボウルに水を入れて、どんぐりをジャブンと入れると……虫食いの実は浮いてきます。
- 浮いたもの → 虫が入っている可能性大なので処分
- 沈んだもの → きれいに洗って天日干し or 風通しの良い場所で乾燥
乾燥はしっかりやらないとカビるので要注意です。
冷凍処理(小さい実や全般に使える)
ジップ袋に木の実を入れて、冷凍庫で一週間程度。
これで中にいる虫をやっつけられます。
松ぼっくりやモミジバフウみたいに飾りで使いたい実にもおすすめです。
塩水処理(どんぐりや小さい実向け)
塩水に木の実を浮かべると、虫食いのものが浮いてきます。
水選別と似ていますが、虫や卵の駆除にも有効です。乾燥させればカビの発生も抑え、保存性を高めることもできます。
漂白処理(松ぼっくり向け)
松ぼっくりは「漂白剤に漬ける」とおしゃれな白い松ぼっくりに変身します。
虫対策にもなり、クリスマスのリースやツリー飾りにぴったり。
やり方は簡単。
- バケツに水を張り、漂白剤を薄める
- 松ぼっくりが浮いてこないよう重しで沈める
- そのまま1日以上置く
- 取り出してしっかり水洗い
- 天日干しでしっかり乾かす
木の実ごとのポイント
どんぐり

- 煮沸は腐る可能性があるのでおススメできません!
- 水選別 (塩水)→ 洗浄 → しっかり乾燥
- 虫とカビを防ぐなら乾燥が命です。
くるみ

- 果皮を外してから乾燥。
- 食用にするにはさらに殻を割って中身を取り出す必要あり。
- ここはちょっと工程が多いので、別記事で「くるみを食べるまでの流れ」を紹介しようと思います。
松ぼっくり

- 煮沸。洗うとかさが閉じてしまうので、沸騰したお湯にそのまま入れて10分ほど茹でる。
- 自然乾燥でも使える。
- 漂白でホワイト加工すれば、クリスマスシーズンに大活躍!
モミジバフウやスズカケの実

- 見た目が可愛いけど虫が出やすい。
- 冷凍処理で安心して使えます。
保存方法のコツ

- 完全に乾燥させてから保存すること
- ジップ袋+乾燥剤、または紙袋で風通し良く
- 湿気を避けるのが大事
- 子どもと一緒にラベルを貼って「木の実図鑑」にすると、観察&学習にもなります
まとめ
木の実は「拾ったあとどう処理するか」で長持ちするかどうかが決まります。
- どんぐり → 水選別&乾燥
- 松ぼっくり →煮沸&乾燥 or 漂白で白い松ぼっくりに
- くるみ → 果皮処理 → 食用加工は別記事で紹介予定
拾うことが楽しい木の実ですが、拾った後もいろいろと楽しむことができます。
しっかり準備すれば、工作や飾り、観察などで子どもと長く楽しめますよ。
自分で拾った木の実で、ハロウィンやクリスマスの飾りを作れるよう、今のうちから準備してみるのはいかがですか?
ではまた。――パパちん
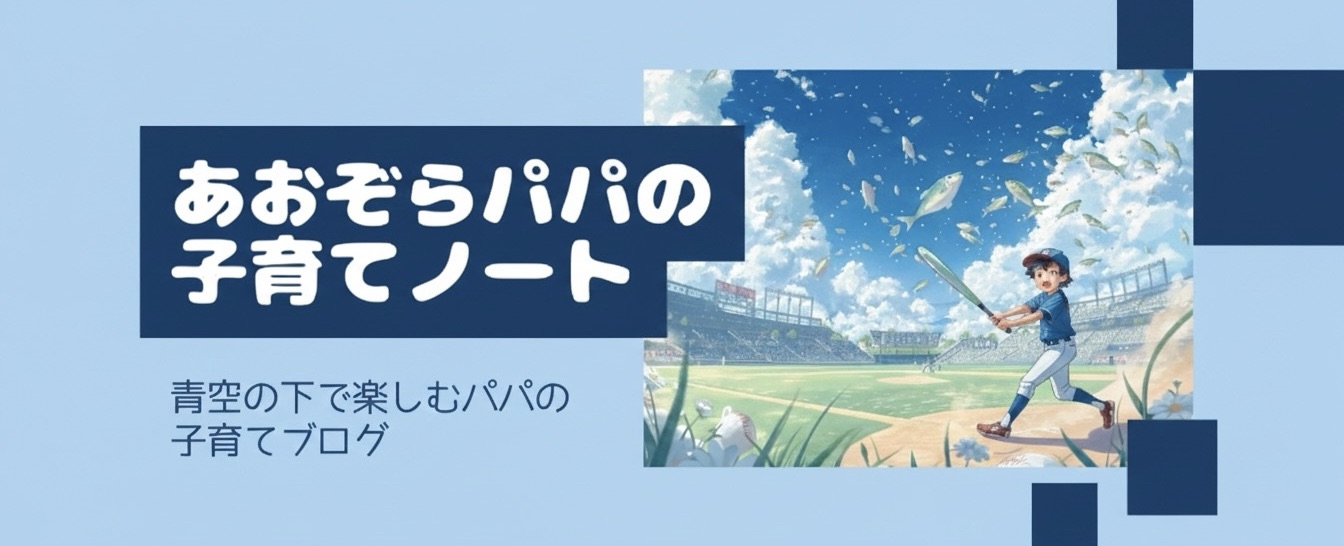
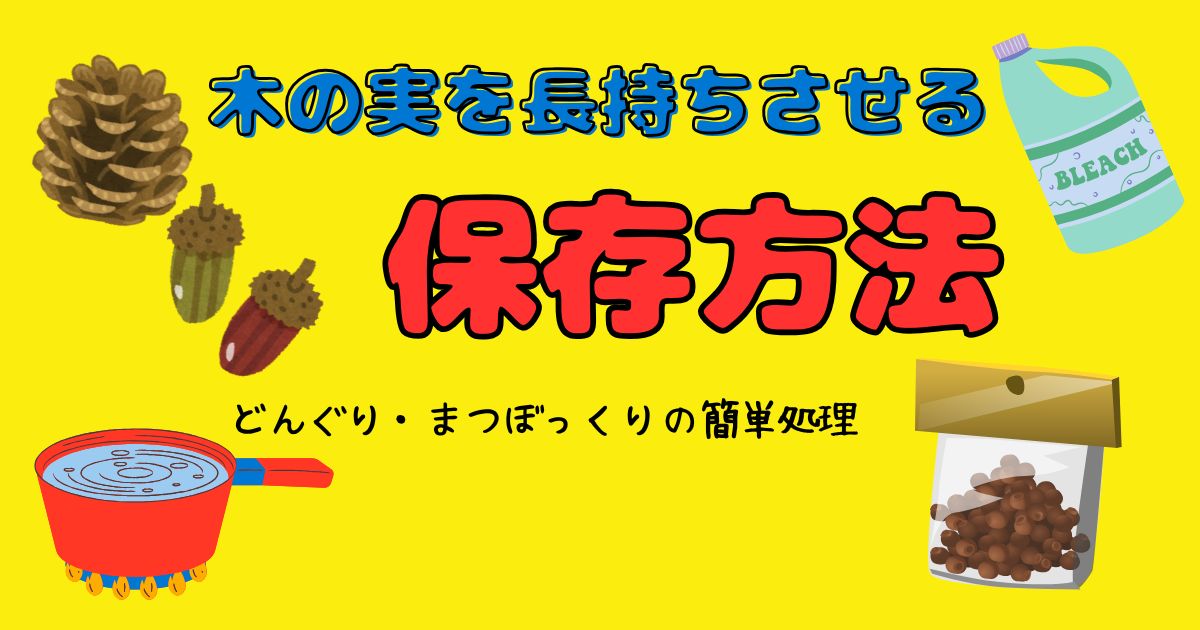



コメント