
どーもパパちんです。
秋になると、なんだか散歩したくなりません?
公園や神社を歩いているだけで、子どもが「パパ!どんぐりあったー!」って走っていくんですよね。ポケットいっぱいに木の実を詰め込み、帰り道はずっしりで、今にもズボンが落ちてしまいそうなほどに。(笑)
でもその姿を見ると、「こういう小さな発見が子どもには宝物なんだな」ってしみじみ感じます。
木の実拾いって、お金もかからないし、特別な準備もいらない。それなのに、自然と触れ合えて、子どもが夢中になれる最高の秋遊びなんです。
この記事では、
- 子どもが喜ぶ木の実の種類
- 拾うときのコツや注意点
- 木の実以外にも集めたい自然素材
- 保存や活用のヒント
を、実体験をまじえながら紹介していきます。今のうちに集めておけば、冬にはクリスマスの飾りづくりにもつながりますよ!
木の実拾いが子どもに人気の理由

自然と触れ合える秋の外遊び
秋になると、外を歩くだけで落ち葉のじゅうたんが広がり、どんぐりや松ぼっくりが転がっています。子どもって、そういうちょっとした自然の変化にすぐ気づくんですよね。
うちの子も、普段は「疲れた〜」って言いながら歩くのに、どんぐりを見つけた途端にダッシュ。自然の中では不思議と体力が湧いてくるみたいです(笑)。
外遊びの中でも木の実拾いは、散歩やお出かけの延長で楽しめるのが魅力。わざわざ道具を買ったり場所を予約したりしなくても、すぐ始められるのも親としては助かりますよね。
宝探し感覚で夢中になれる
子どもにとって木の実は「ただの落ちてるもの」じゃなくて「宝物」そのもの。
「誰が一番大きなどんぐりを見つけられるか!」なんて言うと、兄弟で真剣勝負が始まります。ときには「ぼくの方が多い!」とケンカになるくらい(笑)。でもそのやりとりすら楽しい思い出になります。
同じ木の実でも形や色が少しずつ違うので、「これは帽子つき!」「これは細長い!」なんて観察しながら集めるのも子どもの好奇心を刺激してくれます。まさに秋だけの自然の宝探しです。
子どもが喜ぶ木の実の種類
どんぐり(定番・工作向き)

秋の木の実といえば、やっぱりどんぐり。公園や神社の境内を歩けば、あっという間に子どもが拾い集めてきます。
うちの子はポケットに詰め込みすぎて、家に帰ってから洗濯機の中で「ガラガラガラ…」と音がして発覚(笑)。そんなことが日常茶飯事です...
どんぐりは種類も豊富で、帽子がついているものや、細長いものなどバリエーションが楽しめるのも魅力。工作にも向いていて、顔を描いたり、オーナメントにしたりと遊びの幅が広がります。
松ぼっくり(リース・ツリーの飾りに)

松の木の下に行くと、大小さまざまな松ぼっくりが落ちています。見つけると子どもはつい両手で抱えて持って帰ろうとするんですよね。
松ぼっくりは、乾燥具合によって形が全然違うのもおもしろいところ。ギュッと閉じたものもあれば、カサが開いて大きく見えるものもあります。冬のリースやツリーの飾りに大活躍するので、集めておくと後から「とっておいてよかった!」となるアイテムです。
栗・クルミ(食べられるけど拾える場所を確認)

イガに包まれた栗を見つけたときの子どもの喜びようといったら、もう目をキラッキラさせて「見て!トゲトゲの宝物!」って感じ。
ただ、素手で触るとケガをする恐れがあるので、むやみに手で触らないように、手袋や靴底でイガを剥くようにしましょう。
クルミも川沿いや公園で拾えることがあります。殻を割って食べることもできますが、管理されている場所では持ち帰り禁止のことも多いので要注意。栗やクルミは「食べられる=自由に拾える」ではないので、必ずルールを確認してからにしましょう。
銀杏(食べられるけど扱い注意)

秋の公園を歩いていると、強烈な匂いで「ここに銀杏が落ちてるな」とすぐにわかりますよね(笑)。子どもはその匂いにも興味津々で「なに?この匂い!臭い!」と臭いだけでテンションが上がります。
銀杏は食べられる木の実ですが、皮をむいたり下処理をしたりと大人でも手間がかかります。しかも素手で触るとかぶれたりするので、子どもが拾いたがるときはビニール手袋や火ばさみを用意しておくと安心です。
木の実拾いのコツと注意点
1. 木の実が見つかりやすい場所を選ぶ
木の実は、公園や森の遊歩道、河原の近くなどで見つかります。特にドングリやクリの木の下は狙い目。実は、カブトムシやクワガタが集まる木でもあるので、夏に虫取りをした場所を思い出して探すと見つけやすいです。
2. 拾うときは袋よりもカゴやネットが便利

ビニール袋にたくさん詰めると、中で湿気がこもってカビや虫が発生しやすいです。
通気性のいいカゴやネットを持っていくと、拾った瞬間から保存状態も良くなります。
3. 虫食いやカビのある実は避ける
見た目がきれいでも、小さな穴が空いていると中に虫がいる可能性大。白っぽく変色しているものも避けましょう。
子どもに「これはキレイ」「これは虫さん入り」と一緒に選別させると、ゲーム感覚で楽しめます。
4. 拾ったあとの処理も忘れずに
持ち帰った木の実は、水に浮かべて沈んだものを残す「水選別」をすると失敗が減ります。
さらに一度天日干しして乾燥させてから保管すると、長持ちします。
5. 公園や自然でのマナーを守る
・木を揺らして落とすのはNG(他の人に当たったり、気を傷つけてしまう恐れが)
・大量に持ち帰らず、遊ぶ分・飾る分だけにする
・地域によっては採取禁止の場所もあるので、看板などをチェック
木の実以外にも集めて楽しい自然
木の実拾いのついでに、ちょっと目を向けると「これも持って帰って遊べるじゃん!」という自然素材がいろいろ落ちています。子どもと一緒に「宝物探し」をする気分で集めてみると、秋の散歩がぐっと楽しくなりますよ。
落ち葉(押し葉や飾りに)

秋といえばカラフルな落ち葉。黄色や赤に色づいた葉っぱを拾ってノートに挟んでおけば、きれいな押し葉ができます。
うちでは子どもが「この葉っぱはハートみたい!」なんて言いながら夢中で集めてました。集めた落ち葉は画用紙に貼って絵にしたり、リースの飾りにしたりと遊び方もいろいろ。
ツル(リースの土台に使える)
公園の端っこや雑木林でよく見かけるツルは、ぐるっと丸めるとリースの土台になります。
クリスマスやお正月に使うリースを、秋のうちから「自分で拾った素材」で作れるのは子どもにとって特別な体験。親の僕から見ても「おお、ちょっと本格的じゃん!」と感心しちゃいます。
枝(オーナメントや工作に)
太さや長さの違う枝も、子どもの想像力次第で立派な工作材料に。
「魔法のつえ」になったり、「小人の家の柱」になったり。冬になったらツリーのオーナメントに吊るす飾りにしても映えます。折れた枝でも、子どもにとっては立派な宝物なんですよね。
集めた木の実はどうする?保存と活用のヒント
せっかく子どもと一緒に拾った木の実。持って帰ってそのまま置いておくと、実は「虫が出てきた!」なんてこともあります…。ここでは、家庭でできる簡単な保存と活用の工夫を紹介します。
虫がわきやすいので下処理が大切
どんぐりや松ぼっくりなど、自然の中で落ちていた木の実には小さな虫が入り込んでいることが多いです。
我が家も初めてどんぐりを拾ったとき、何もせず机の上に置いていたら、数日後に小さい穴から虫が出てきてビックリしました…。
だからこそ、持ち帰ったらすぐに下処理をしてあげるのがおすすめです。
保存方法の基本(冷凍・煮沸・塩水)
木の実の保存には大きく3つの方法があります。
- 冷凍:ジッパー付きの袋に入れて数日冷凍するだけ。虫対策に有効。
- 煮沸:鍋でしっかり煮て乾かす方法。工作用には最適。
- 塩水:塩水の中に3日程漬けた後しっかり乾燥させる方法。
特にどんぐりや松ぼっくりは、冷凍か煮沸をしてから乾かすと安心して工作や飾りに使えますよ。
今のうちに集めておけば、冬のクリスマス工作に使える!
秋に拾った木の実やツル、枝をちょっと工夫して保存しておけば、冬のクリスマスに大活躍。
たとえば、松ぼっくりを白くペイントすれば雪をかぶったツリー風に。どんぐりに顔を描けばサンタさんやトナカイに変身。
「秋の宝探し」が「冬の飾りつけ」にまでつながると、子どもも「拾ってよかったね!」と大満足です。
まとめ|秋の外遊びを楽しんで冬まで活かそう
秋の木の実拾いは、子どもと一緒に自然と触れ合える最高の外遊びです。
どんぐりや松ぼっくりを拾いながら「これは何に使えるかな?」なんて話していると、まるで宝探しをしているみたいで夢中になります。
拾った木の実は、そのまま眺めるだけでも楽しいし、下処理をして保存しておけば、冬のクリスマス工作にもつなげられる。季節をまたいで楽しめるのが大きな魅力ですね。
ぜひこの秋は、子どもと一緒に袋を片手に近所の公園や森を歩いてみてください。
自然の中に思わぬ発見があって、親子で笑顔になれるはずです。
ではまた。――パパちん
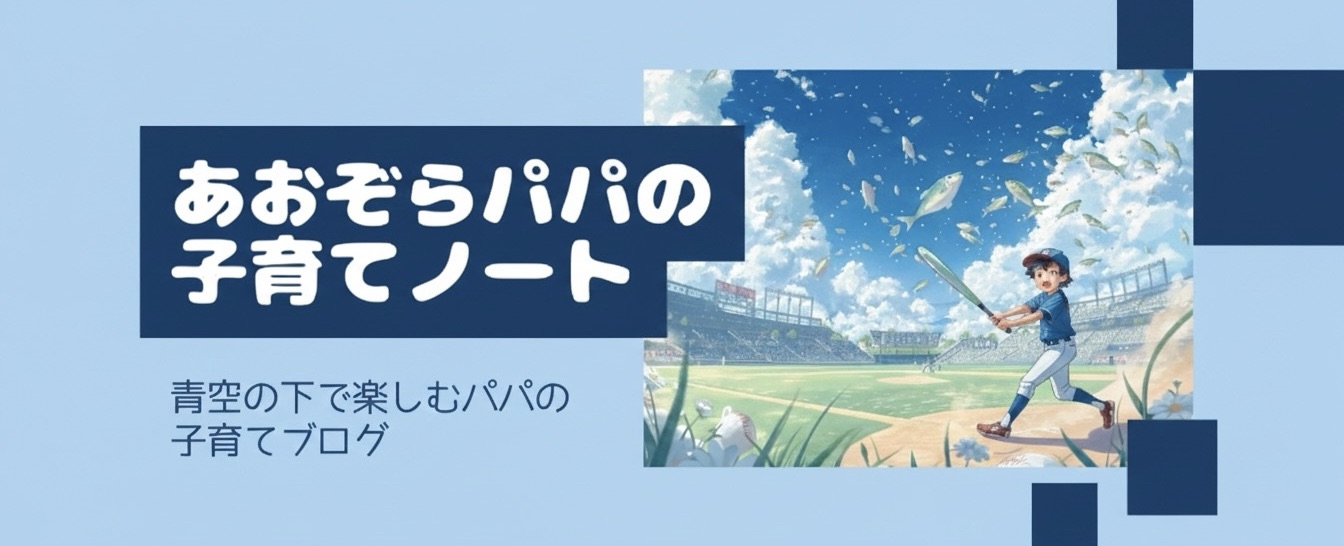




コメント